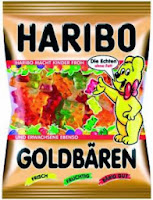私のレッスンでは、しばしば「身体と楽器の関係」について話題になります。フルートを吹く上で、とっても
「効く」であろう本がありましたので、ご紹介します。
自然体のつくり方 - レスポンスする身体へ
斎藤孝著
Amazonのレビューなどでも紹介されていますが、私なりにまとめてみます。
一流のスポーツ選手・武道家・音楽家・舞踊家・また伝統文化を継承する大家の人たちは、共通して持っている身体感覚があります。それが「自然体」です。
この「自然体」が、各人の身体を通したパフォーマンス能力を、最大限発揮させます。
『自然体』とはなんでしょうか?
からだに中心軸が通っていて、安定感があり、リラックスしながらも覚醒しているような身体のありかた。単なる脱力の状態とは異なります。
そしてこのような状態は『
上虚下実(じょうきょかじつ)』によって得る事が出来ます。
『上虚下実』とはなんでしょうか・・・?
 上半身の力は抜けていて、下半身は地に足がついた力強さと粘り強さがある。臍下丹田(せいかたんでん)には力が入るが、みぞおちの力は抜けている状態のこと。
上半身の力は抜けていて、下半身は地に足がついた力強さと粘り強さがある。臍下丹田(せいかたんでん)には力が入るが、みぞおちの力は抜けている状態のこと。
自然体からレスポンス(=反応)する身体へ
臍下丹田を中心にした呼吸、上虚下実の状態では、のど元やみぞおちがほぐれて、呼吸が深くなります。呼吸が深くなると余裕が生まれ、
レスポンスしやすい体となります。(※注:つまり、楽器を吹く際に必要な
神経伝達を、よりスムーズなものとするのです。それは各人の持っているポテンシャルを、より発揮しやすい身体となります。)
レスポンスが上手くいかない状態とは…?
硬くなっていたり、閉じていたり、鈍くなっていたりする状態のこと。身体のサインとして表れるのは
「肩に力が入って力んでいる」「眉間にしわを寄せる」「のど元を締める」「みぞおちを固くする」「手首の力が抜けない」など、身体のあちこちに「ブロック」を作ってしまうことです。(※注:フルートの場合、これらの現象はのびやかな呼吸をさまたげ、指や舌への神経伝達を困難にします。)
精神への作用
上記のような身体感覚は、精神へも作用します。
「集中力」「決断力」「行動力」を高めます。自然体とは(身体の)内側へのみの集中した状態ではなく、むしろ外側へ配慮する、開かれた構え、ということです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
本の概要をお伝えするのは、なかなか難しい…。舌足らずな表現だとは思いますが、要点はお分かり頂けたでしょうか?
頭で理解すること、そして体が覚え、自動化することは、過程が違います。体は同じ事を継続しなければ、筋肉や神経に定着しません。それでも先ず「理解」の方向が違っていては、時間をロスするばかりです。
私は何人かの生徒さんと、上記の一部を試してみました。
臍下丹田を源として、頭頂は天へ伸びゆくイメージです。(アゴは大地の方へ)
片足で立つなどすると、体の中心軸を持っているかどうか、更にはっきりします。このように得られた呼吸は非常に安定し、音にも生命が宿ります。
また小6のAちゃんは、この立ち方で音にキープ力がついただけでなく、集中力が増し、この頃はとても充実したレッスン内容になってきました。
子どものレッスンをしていると、全身がくねくねとして頼りなく、しっかり立つことすらおぼつかない子が少なくありません。当然呼吸の源も不安定で、音が決まらないのです。(一方で、子どもは自然を取り戻すのも早いのですが。)
「しっかり立つ」という行為に対し、メンタルな作用が得られるというのは、興味深いところです。
余談ですが、吹奏楽の現場では、楽器を持つやいなや夏のコンクール用の難しい曲を与えられ、子供はそれをがむしゃらになってさらうので、どこもかしかも不自然で、無駄に緊張した奏法を身につけてしまうケースが見られます。このブロックを解くのは容易ではありません。
また大人も、身体の使い方のパターンに関して、長年の蓄積があるために、無くて七癖だなぁと感じる事があります。私自身にも言える事ですが、
身体に対する客観性を保つ、(願わくば耳を通じて)身体と会話する、という感覚がとても大切です。
【関連記事】
ジャン・フェランディス 公開レッスン
http://klangjapan467.blogspot.jp/2015/04/blog-post_10.html
高木綾子さん 公開レッスン
http://klangjapan467.blogspot.jp/2014/12/blog-post.html
ロングトーンのススメ ①
http://klangjapan467.blogspot.jp/2014/11/blog-post_6.html